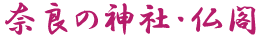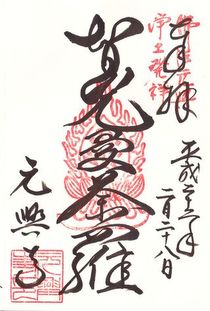 |
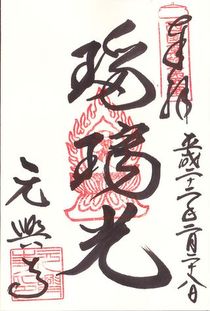 西国薬師四十九霊場 |
| 【元興寺のサイトへ】 | |
|---|---|
|
住所/〒630-8392 奈良市中院町11
|
|
 世界遺産の碑 |
真言律宗。南都七大寺の一つに数えられる寺院。 |
 東門 |
 極楽堂 |
|
元興寺の歴史は、藤原・奈良時代は崇佛派の蘇我氏による仏教政策や、朝廷の管理下にある三宝常住の官寺であった。しかし平安時代になると、律令制度の崩壊によって、官大寺は無くなり、権門寺院でもある興福寺や東大寺の支配下に組み込まれた。更に鎌倉時代になると、元興寺は伽藍が解体し、堂塔が分散し、その中で僧坊遺構の極楽坊は室町時代に、興福寺大乗院の支配となり、坊主は己心寺(大安寺)門流(真言律の西大寺流)とされた。江戸時代には、西大寺直門として多くの重役を輩出した。
|
|
 浮図田と禅室 |
 浮図田と小子坊 |
|
(左上)禅室 国宝。念仏道場。建築様式としては鎌倉時代の大仏様を示しているが、構造材は奈良時代以前の古材が多く再利用されている。本堂と同様に南流れの屋根の一部に行基葺古瓦が残っている。
|
|
 浮図田 |
 講堂跡礎石 |
|
(左上)浮図田(ふとでん) 寺内及び周辺地域から集まった2500余基の石塔、石仏類で、総称して浮図と言う。新たに田んぼの稲のように整備されたもの。主に鎌倉時代末期から江戸時代中期のものが多い。浄土往生を願って、極楽坊周辺に造立した供養仏塔である。
|
|
 かえる石 |
 北門 |
|
(左上)かえる石 江戸時代の奇石を集めた「雲根志」(日本で最初の石の専門書)に載っている大阪城の蛙石。河内の川べりにあった殺生石だったようだが、後に秀吉が気に入って大阪城に運び込まれたと言われている。大阪城にあった頃は堀に身を投げた人も必ずこの石の下に帰ると言われた。福かえる、無事かえるの名石として、毎年7月7日に供養される。 |
|