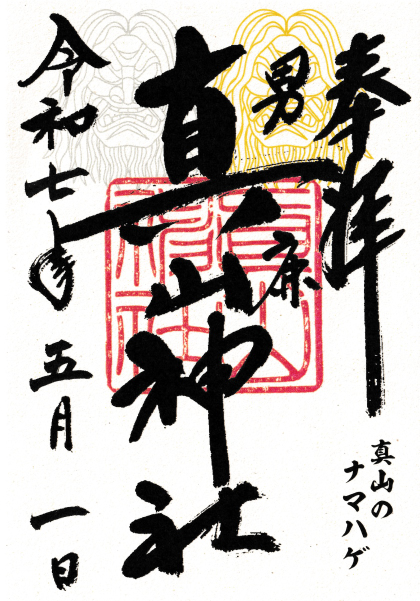 |
| 【真山神社のサイトへ】 | |
|---|---|
|
住所/〒010-0685 秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97 |
|
 一の鳥居 |
 仁王門 |
|
御祭神は |
|
 拝殿 |
 拝殿神額 |
|
平安時代の貞観年中(859〜877年)に円仁慈覚大師によって湧出山は二分され、北を真山、南を本山としたと伝えられる。それ以降修験の信仰が高まり、天台僧徒によって比叡山延暦寺守護神の赤山明神と習合された。南北朝時代には真山別当 |
|
 薬師堂 |
 神楽殿 |
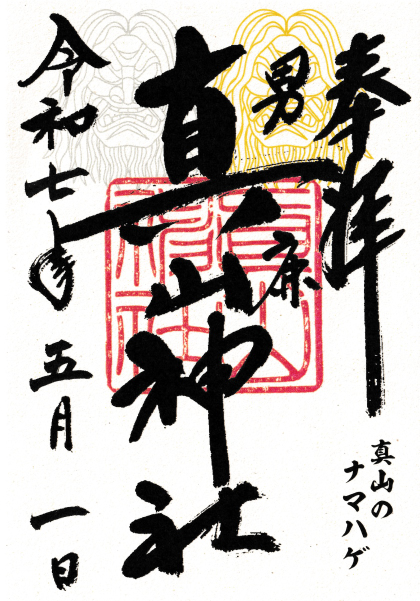 |
| 【真山神社のサイトへ】 | |
|---|---|
|
住所/〒010-0685 秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢97 |
|
 一の鳥居 |
 仁王門 |
|
御祭神は |
|
 拝殿 |
 拝殿神額 |
|
平安時代の貞観年中(859〜877年)に円仁慈覚大師によって湧出山は二分され、北を真山、南を本山としたと伝えられる。それ以降修験の信仰が高まり、天台僧徒によって比叡山延暦寺守護神の赤山明神と習合された。南北朝時代には真山別当 |
|
 薬師堂 |
 神楽殿 |