|
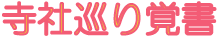
砥部焼 砥部では江戸時代の半ばまで陶器が作られていた。1775年に厳しい財政状況下にあった大洲藩の命により磁器の開発が始まった。1777年に杉野丈助が白磁の焼成に成功、1818年に向井源治が川登陶石の発見、1848年には井岡太蔵がレンガを使った窯をつくり進歩を遂げ、1893年のシカゴ世界博覧会で1等賞を獲得して世界に進出した。
昭和初期の世界的な不況と太平洋戦争の勃発で、砥部の焼物は戦後壊滅的な打撃を受けたが、戦火を逃れた陶工たちは手仕事を受け継ぎ、意欲的な創作と技術の向上に取り組み、今日の砥部焼を作り上げた。
その結果、砥部焼は1976年に陶器の世界では全国6番目となる「伝統的工芸品産地」として指定された。
⇒砥部焼のサイトまで
|
![]()



